登校をめぐって子育てに悩む親たちとの初めての「お話会」
登校拒否を考える親と子の会「ブルースカイ」は、2024年4月にオープンした教育支援センター「SaSaLAND(ササランド)」と、市内の教育支援センターに登録している子どもの親を対象にした親の会「ツナガル」との共催で、25年5月25日に学習会を開き、学校に通わず家で学んでいる子を育てている親など17人が参加しました。
テーマは「ホームスクーラーって知ってる? 様々な事情でお家で過ごす子どもたちがいます」。
「ホームスクール」とは、ホームスクーリング、ホームエデュケーションとも呼ばれ、学校に通わず家庭を拠点にして、子ども自身の興味や関心を尊重した教育方法です。
主催したブルースカイは、子どもの不登校で悩む親たちが1990年に立ち上げ、「例会」や「親の会」を開くなどして、学校に通わずに学ぶ子どもと親たちの居場所づくりをしてきた団体です。

長野市には、SaSaLANDを含めて、8カ所の教育支援センターがあります。教育支援センターは、学校に行きにくくなっていたり、行けない状態が続いていたりする小中学生のための施設です。
ツナガルは、SaSaLANDに登録する子の親である丸山彩美さんと金子久美子さんが24年6月に立ち上げ、毎月1回親の会を開いてきました。ブルースカイ代表の松田恵子さんは、ツナガルの親の会に毎回参加。親たちと交流する中で、「ホームスクールという言葉を初めて知った」という声を聞き、「多様な学びの選択肢としてホームスクールの考え方を知ってほしい」と、丸山さんと金子さんと共に今回のおはなし会を企画しました。
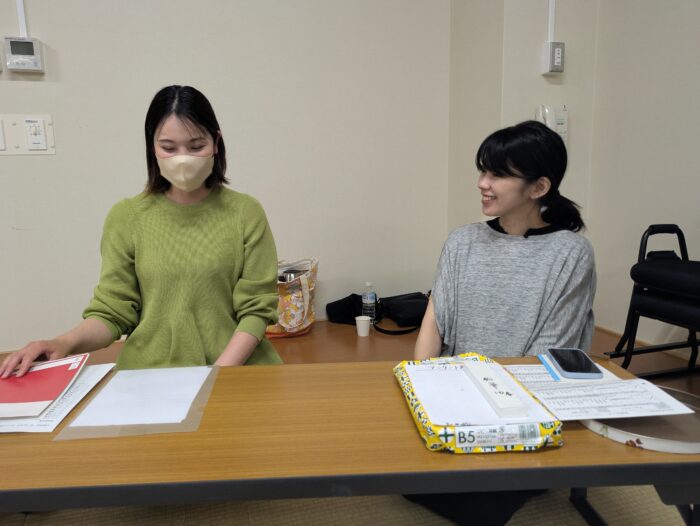
一人ひとり個性が違う子の学びをどう進めるか
学習会では、自身も不登校を経験しホームスクールを選択した3人の子どもたちを育てている北海道の鈴村唯さんの動画を視聴した後、家庭でホームスクールを実践している長野市の小林律子さんと、子どもの頃にホームスクールで育ち、現在は社会人である北村しずかさんの体験談を聞きました。

小林さんは小学4年生と2年生の女の子を、ホームスクールで育てています。「子どもたちは小学校に行き、私は仕事に行って帰ってきたら習い事、ご飯を作って…と思い描いていた日常がなくなったことで、それまでは子どもたちを自分の中の『当たり前』にあてはめて見ていたことに気が付きました。『この子たちは一体何をしたくて、どんな子どもたちなのかな』と、子どもたち自身のことを見るように考え方を変えました」と話します。
ブルースカイの松田さんに連絡を取ったり、SNSなどで情報収集し、子どもたちの過ごし方を模索する中で、好きなように散らかしてよい大きな作業用テーブルを購入したり、ゲーム用の部屋を作ったりと環境づくりをしてきました。「ホースクールって、算数や国語などを学校の代わりに親が教えるイメージでしたが、ホームスクールの本質は自分のペースを大切にしながら、家で趣味や関心のあることに没頭できるところにあります。子どものやりたいことを邪魔せずのびのびとやらせてあげることが大事ではないかと思っています」
姉妹の二人はそれぞれ個性が違い、過ごし方も違います。次女はSaSaLANDに半日通っていますが、長女は家で過ごすことを選択しています。「家が一番好きで家を選んでいるのですが『SaSaLANDにも行けなかったんだね』と言われてしまうことがあります。『家で過ごすことが好きな子は自分でそれを選んでいるから、それはそれでいいんだよ』ということを皆さんにもっと伝えたいと思っています」と強調していました。

二人目の話し手の北村さんは、小学1年生頃から学校への行き渋りが始まり、小学 5~6 年生頃からは完全に家で過ごすようになったそうです。「このままだと将来仕事に就けないのではないかな?と、将来への不安がすごくありました。でも、勉強をどう進めてよいかわかりませんでした」
北村さんの母が、ブルースカイに参加する中で、東京でフリースクールを運営するNPO法人「東京シューレ」が行っていた、ホームスクールの子どもたちを支援する「ホームシューレ」を知り、ホームシューレのサポートで勉強を進めるようになりました。また、親が買ってくれたパソコンで、自分の好きな手芸のことを調べたり、浴衣を自分で縫ったりと、自分の興味から世界を広げていきました。
二人の体験談の後、小林さんと北村さんを車座に囲み、参加者たちはホームスクールを進める上での疑問や悩みを共有しました。参加者からの「ゲームは時間制限をするべきか、しなくていいのか。ゲームを巡って子どもと言い合いになってしまう。ゲームとどう付き合ったらよいか」と質問に、小林さんは「うちは時間制限なしでした。するとゲームをやらない時間も出てきました。とことんやって、次の何かに手が伸びるまで見守っていても良いのかなと思います」と長女の2年間の変化を話しました。
「久しぶりに自分で算数の学習をしようとタブレット教材を開いたら、全くわからない内容で『もういい!』と放り出してしまった。わからなくて不安を感じているのは子ども自身だが、親は一緒にどう乗り越えればよいか」との問いには、北村さんが「私も算数が理解できなかったけれど、『どうしてこういう答えになるのか』の根本がわかったらおもしろくなりました。いろいろな教材を買ったりするのは大変だと思いますが、自分にぴったり合うものに出合えるとよいのではないでしょうか」とアドバイス。参加者は「算数一つをとってもいろいろな選択があって、いろいろなアプローチの仕方がある。学校での学びはその 1 つに過ぎず理解が深まりました」とうなずいていました。
悩みを共有し、共感することで心が軽くなる
今回の学習会を共催したツナガルの丸山さんは、小学 5 年生の子を育てています。子どもは1年生から不登校でしたが 4 年生の夏頃から学校に行けるようになったそうです。「本当にどん底を経験して、お互いに暗いトンネルの中を歩いていました」と振り返ります。
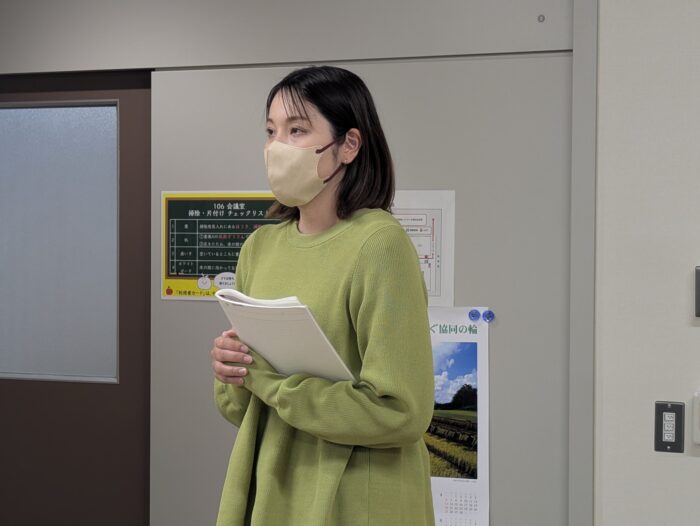
誰に話せばよいか、助けを求めてよいかわからない―そんな状況にいた時、丸山さんは同じように不登校の子を育てる保護者同士で交流する会に参加。「話すことで気持ちが軽くなり、共感できる人が一人でもいれば気が楽になることを実感しました。身近には保護者同士が定期的に話せる場がなかったので、親の会をつくろうと考えました」
子どもが学校に通えるようになっている現在は、丸山さん自身は親の会にあまり参加できていないそうですが、SaSaLANDのスタッフの協力で親の会の開催を続けています。「自分の仕事もある中で、志を持ってボランティアを続けるのは大変なことです。松田さんの活動には頭が下がります」と丸山さん。親の会を開くにあたり、松田さんがノウハウを提供し、運営で困った時にはサポートしています。松田さんは「SNSなどで便利になっていますが、こうしてリアルで会うことの大切さを感じてほしい。皆さん一つ一つ違う家庭の中で、できることをしていってほしいと思います」と話していました。
取材・執筆/ ソーシャルライター 松井明子











