「若穂にこんなにも多くの民話があったなんて!」予想以上の話数と内容の多様さ・豊富さに圧倒され、身震いした感動と衝撃は今でも忘れられません。
民話は、先人から脈々と語り継がれてきた口伝の「文化」です。お話の中には、土地の歴史や動植物とのふれあい、人間の営み・心情・愛情・戒め、自然や神仏に対する純粋な信仰心・感謝・畏敬の念などが盛り沢山に詰まっていて、今を生きる私たちに多くの事を教えてくれます。
風化する前に記録化し、伝え続けよう!と、平成31年4月に地域の有志で設立した「若穂民話の会」は、6年間で85話のお話を採集・編纂して『若穂のみんわ第一集~第四集』にまとめました。更に民話紙芝居の作製・上演、SBCラジオ朗読番組への出演、令和6年には『若穂のみんわカルタ』を発行し、民話紹介活動を継続しています。
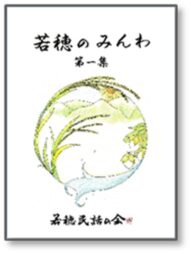
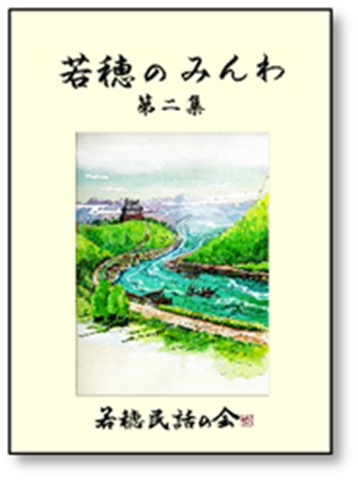
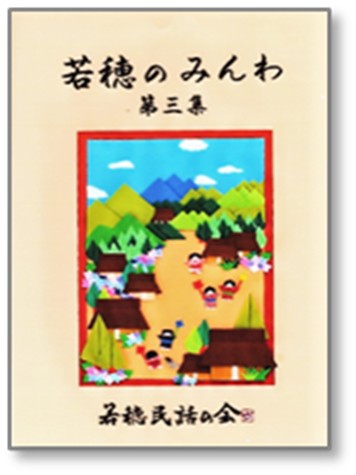
ひとつのお話を作るのにも、会員それぞれに思い入れやこだわりがあり、納得がいくまで熱い議論を侃々諤々(かんかんがくがく)と戦わせてきた仲間(男性5名女性5名、63歳~91歳)は、今では阿吽の呼吸でサポートしあえる同志となりました。民話を通して郷土を知り・愛し・誇りを育み、郷土や己の未来に少しでも役立てたいと始めた活動は、自らの生きる力となり、生活を彩り、日々の生き甲斐を与えてくれます。
現在は活動の主軸を地域学習に移して、地区内の小・中学校で、子どもたちと一緒に地域探訪や歴史学習に取り組んでいます。また魅力ある若穂の風土を多くの方に知って頂くため、“湯~ぱれあ”で「若穂の民話を訪ねる」シリーズや、地域公民館と協働で「民話の郷めぐり」などのボランティアガイド活動も実施しています。

ある日の活動中に、一年生の子どもさんから「大きくなったら何になりたいの?」と聞かれ、その時は言葉を濁してしまいましたが、次に聞かれた時には「“妖怪お話ばばさま”になりたいんじゃあ!」と答えたいなぁ。
執筆:「若穂民話の会」事務局長 穂谷真弓
初出:長野市民新聞 NPOリレーコラム「空SORA」2025年5月掲載









